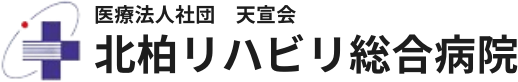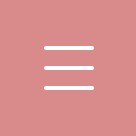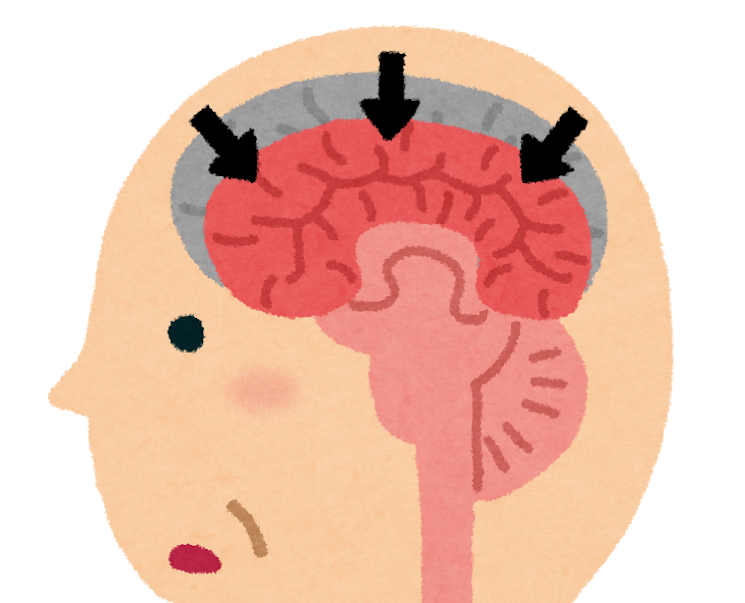健康コラム COLUMN
なぜ薬を飲む時間は決まっているの?
なぜ薬の飲み時間が決められているのかご存じでしょうか?
薬にそれぞれ「食前」「食後」「食間」など飲む時間帯が決まっているのは、薬がより効果的に安全に効くようにするためです。
食前とはご飯を食べるおよそ30分前、食後とはおよそ30分後を言います。食間とは「食事と食事の間」のこと。一般的には食後2時間を指し、空腹時とほぼ同じ意味です。
薬を飲む時間帯は、薬の性質や効能、副作用などを考慮して決められます。例えば吐き気止めは、その効能から食前に飲む必要がありますし、胃腸を荒らす副作用がある薬の場合、食直後に飲むことが多いです。
なかには、糖尿病の薬で食直前に服用しないと十分に効果が発揮されない薬もあります。これは食後の血糖値の急上昇を抑えるための薬で、食直前とは食事を目の前にしてお箸を持つ直前くらいのことです。
ほかに骨粗鬆症の薬で、起床時に十分な量の水で服用した後、30分間身体を起こし、水以外のものを口にしてはいけない薬もあります。この薬は他の薬や飲食物と相互作用があり、食道などにつくとそこが潰瘍になってしまうことがあるので、胃まで落とす必要があるためです。
しかしながら、食後でも食前に飲んでも、あまり効き目に違いがない薬もあるので、自分が忘れずに飲めるタイミングで飲んでも、効果や安全性に問題がないか聞いてみてもいいですね。一番大事なのは薬を飲み忘れないようにして、効果的に治療することです。

北柏リハビリ総合病院 薬局より